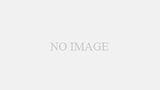PoemBlog ~詩のブログ~ へようこそ。
Each poem is followed by its English translation.
ある集会にて
調子を合わせなくてはならないのですか
ごたごたがもやもやするから
好きではないのですよ
私は遠い
些末も遠い
真上にぶら下がっていた
不安果実がポトン
噛み合わない鎮静と悲哀の余韻
枯草のやるせなさ
窓から見えるのは
コンクリーの打ちっ放しの空
厚かましさが才能の一つなのでしょうね
残る問題はいくつあるのですか
助言はないのですね
未来の立場は求められる集会
分厚い正義に
つきまとう言葉の響きが耳をつんざく
初観察を送信
初接触の感情
滑稽は説明を伏せられる
振動の中心軸は後ずさりする
はずんで見せたりする
店番には商売っ気のない老人が微笑する
私は遠い
哀切も遠い
ミルク雲きれい
クシャクシャヨレヨレワイシャツ
アイロンかけ
テーブルのメモをポケットに忍ばせて
アパートを飛び出す
公園のひんやりとする砂地に吸い込まれた
過去の袖口から
ニョキニョキと定めの腕が伸びる
地平線をつかもうとして
#詩
#詩のブログ
At a Gathering
Must I match their rhythm?
I don’t like the clutter,
the fog of tangled voices.
I am distant—
even trivial things are far away.
From straight above,
a fruit of anxiety drops—plop.
Uneasy calm, the aftertaste of sorrow,
the futility of dried grass.
Through the window,
only bare concrete sky.
Perhaps audacity is one kind of talent.
How many problems remain?
No advice, I see.
The gathering that demands
a future stance—
words of thick righteousness
pierce the ears with their echo.
First observation—sent.
First contact—emotion.
Absurdity keeps its explanation sealed.
The axis of vibration steps back,
pretends to bounce.
An old shopkeeper,
without a hint of business, smiles.
I am distant—
even sorrow is far away.
Milk-white clouds—beautiful.
Wrinkled, rumpled shirt—
iron it flat.
A note from the table,
slipped into a pocket,
I dash out of the apartment.
In the park’s cool sand
I’m drawn inward.
From the cuff of my past,
arms of destiny sprout,
reaching—
to grasp the horizon.
#poem
#poemblog
この詩に込めた思い
集団の熱にまきこまれることへの拒絶から始まった。
声を合わせることに疲れ、沈黙の方が正直だと感じた。
同調のなかで、心は少しずつ輪郭を失っていく。
だがその距離の中でしか見えない光がある。
「ミルク雲きれい」という一行は、
混沌のただ中でふと見上げた空の、無垢な一瞬を描いている。
終盤の「地平線をつかもうとして」は、
諦めきれない生の衝動そのもの。
人と関わりながらも、遠く離れ、
それでもなお生きようとする心の記録である。
Thoughts Behind the Poem
The poem begins with resistance—
a refusal to be swept into the fever of the crowd.
I grew weary of matching voices; silence felt more truthful.
Within conformity, the self slowly fades,
yet only from that distance does a faint light appear.
The line “Milk-white clouds—beautiful” captures
a brief moment of purity amid the confusion of living.
The final image, “to grasp the horizon,”
embodies the stubborn impulse to keep reaching.
It is a record of one who stands apart,
still breathing, still alive, within the noise of others.
有名な雨
光が大地に深く溶け込む
眠れる者が呼び醒まされた
汗をぬぐいソーダ水を飲み干し
塔の頂点を見つめていた
三千色の虹が民家の上に架かる
大地から黒々とした拳ほどの金属片が
塔の頂点まで一気に上がり踊りはじめた
初めに何があったのかを考え
行為そのものではなかったかと考える
片足で歩いてきた道をくるりと振り返ると
驚いたことにもう一方の足が歩いていた
奇跡だと思いながら
その足が来るまで待機した
「これまで長い道のりだったが
この先もそうに違いないだろう」
と大地が呼応した
信号機も標識も街灯もない道だ
(有名な雨)は辺り一面を
容赦なく黒色に塗りつぶした
太陽が姿を消したのは本当だ
(有名な雨)が矢のように降らせる
幻と現実が交差する
(有名な雨)には音がない
#詩
#詩のブログ
Famous Rain
Light seeps deep into the earth.
The sleepers are called awake.
Wiping sweat, I drain the soda,
gazing at the tower’s tip.
A rainbow of three thousand colors
arches above the houses.
From the soil, black fragments—fists of metal—
rise to the tower’s peak and begin to dance.
I think of what came first,
perhaps not a thing but the act itself.
Turning around on one-legged steps,
I find the other foot walking.
A miracle, I think,
and wait until it arrives.
“The road has been long,
and will remain so,”
the earth replies.
No traffic lights, no signs, no lamps—
just the road.
(Famous Rain) paints the land
mercilessly in black.
The sun truly vanished.
(Famous Rain) falls like arrows—
where illusion and reality cross.
(Famous Rain) has no sound.
#poem
#poemblog
この詩に込めた思い
この詩は、世界が静かに再構築される瞬間を描いている。
光が沈み、眠りが醒め、行為だけが存在の証となる。
「有名な雨」は出来事ではなく、内なる転換点としての象徴。
片足で歩くという不完全な存在が、
もう一方の足と再会することで、
“行為そのものが生きること”だと知る。
音のない雨は、破壊でも悲嘆でもなく、
すべてを包み込む沈黙の再生。
その静寂の中に、初めて「真の現実」が姿を現す。
この詩は、喪失のあとに訪れる沈黙の啓示を描いている。
Thoughts Behind the Poem
This poem depicts the quiet reconstruction of the world.
Light sinks, sleep awakens, and only action remains as proof of existence.
“Famous Rain” is not an event, but an inner turning point.
The one-legged traveler finds the other foot—
and realizes that to act is to live.
The rain without sound is neither ruin nor grief,
but a silence that embraces all things.
Within that stillness, true reality begins to appear.
It is a revelation born after loss,
a sacred moment when the world begins again—
wordless, yet unmistakably alive.
#poem
#poemblog
嵐
嵐がやって来そうだ
鉛色の雲が龍のように動いている
龍の鱗がピカリと不気味に光る
嵐が来たならば
公園の木々の葉は飛ばされるだろう
幹と枝だけの姿となるだろう
私は
そのような木々の葉だろうか
私は
そのような木々の葉にならぬように
耐えなくてはならない
龍が睨んでいる
何という恐ろしい形相だろうか
#詩
#詩のブログ
Storm
A storm is coming.
Lead-colored clouds move like a dragon.
Its scales flash with eerie light.
When the storm arrives,
the leaves of the park trees
will be blown away,
leaving only trunks and branches.
Am I one of those leaves?
I must endure—
so that I will not become one of them.
The dragon stares,
what a terrifying face it wears.
#poem
#poemblog
この詩に込めた思い
この詩は、自然の「嵐」を借りて、心の中の「恐怖」と「試練」を描いている。
龍は、外的な脅威であると同時に、内側に潜む巨大な不安の象徴。
嵐にさらされる木々の葉のように、自分の意志が吹き飛ばされそうになる瞬間、
人は試される。
「私はそのような木々の葉だろうか」という問いは、
自己の弱さへの自覚であり、同時に抵抗の始まりでもある。
最後まで立っているためには、恐怖の正体を直視しなければならない。
嵐の中でこそ、人間の芯が問われる。
Thoughts Behind the Poem
This poem uses the storm as a mirror for the mind’s own turmoil.
The dragon is both an external threat and a symbol of inner fear—
the force that strips away what is fragile.
When the wind rises,
the self trembles like a leaf.
The question, “Am I one of those leaves?”
marks the beginning of awareness,
the moment when resistance is born.
To remain standing,
one must face the dragon’s gaze—
the embodiment of fear itself.
In the heart of the storm,
the core of being is revealed.